
この記事では、2025年10月現在の生成AI(Generative AI)ブームが、歴史的なバブル現象の再来であるか、それとも持続可能な技術革新の基盤であるかを、多角的な視点から分析する。生成AIは、テキスト生成、画像・動画生成、さらにはマルチモーダルモデルへの進化により、経済・社会に多大な影響を及ぼしている。しかし、このブームの背景には、低金利環境や投機的熱狂が絡み合い、バブル化の兆候が見られる。
結論として、生成AIブームは現時点でバブルとは言えないが、過熱の条件が整いつつある状況であると評価する。実態を伴う技術進化と、マクロ経済的要因による投機的要素が共存しており、需給逼迫が長期化する可能性が高い。主要論拠は以下の通りである。
- マクロ経済的文脈: ゴードン成長モデルに基づき、低金利期待(rの低下)とAI成長期待(gの上昇)が株価急騰を助長している。2025年の米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ継続が、この環境を強化している。
- 歴史的類似性: ドットコムバブルや鉄道狂時代との共通点が見られるが、生成AI特有の「無限需要」物語と寡占構造が独自性を生む。
- 構造的独自性: NVIDIAやSKハイニックスなどの独占・寡占が需給を長期的に逼迫させ、収益化の不確実性を伴いつつも、技術的価値が支える。
この分析を通じて、投資家や政策立案者は、短期的な熱狂を超えた長期視点の重要性を認識すべきである。
序論:生成AIブームの定義と本質
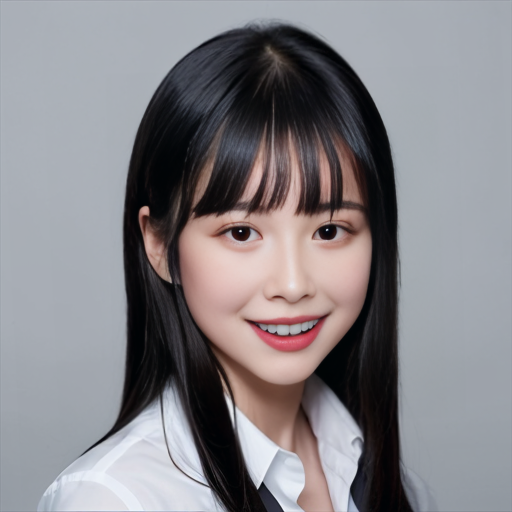
今回のAIブームのポイントは、計算需要の拡大、GPU/HBMなどインフラの供給制約、収益化の不確実性の3点です。
2025年現在、生成AIは急速な進化を遂げており、ブーム初期の文章生成AIから動画生成やマルチモーダルAIへの移行が顕著である。このブームは、単なる技術トレンドではなく、半導体需要の爆発、データセンター投資の拡大、エネルギー消費の増大を伴う経済現象として、世界経済を駆動している。生成AIの核心は、大量のデータと計算資源を活用した創造性生成にあり、これが産業変革を促している。生成AIブームの本質を特徴づける要素は以下の3点に集約される。
- 計算需要の無限拡大: LLM(Large Language Models)のスケーリング法則(Chinchilla法則など)により、モデルサイズの増大が継続し、動画・3D生成の進化がさらなる需要を生む。2025年のトレンドとして、AIエージェントの台頭が計算リソースを「無限に」押し上げている。
- インフラ投資の集中: GPU(NVIDIA主導)、HBM(High Bandwidth Memory)の供給制約が続き、MicrosoftやGoogleなどのクラウドプロバイダーが巨額投資を続ける。このボトルネックが関連株価を押し上げている。
- 収益化の不確実性: AI導入がビジネス効率を向上させる一方で、多くの企業が収益モデルを確立できていない。2025年の報告では、生成AIの商用化が進むものの、ROI(投資収益率)の低さが指摘されている。
この記事では、このブームがバブルか否かを、理論的枠組み、議論の対比、歴史比較を通じて検証する。分析の基盤は、2025年現在の市場データと専門家意見を参考とし、客観性を重視する。
理論的枠組み:バブル分析のためのツール
生成AIブームを評価するためには、市場心理を超えた構造分析が必要である。ここでは、経済モデルと歴史的パターンを用いて、バブル発生の条件を検討する。
ゴードン成長モデルによる株価評価
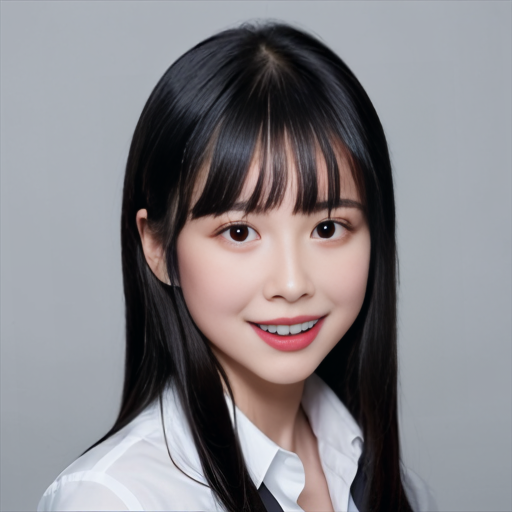
低金利で業績成長期待が高い時に、株価は急騰しバブル化しやすくなります
株価の基本モデルであるゴードン成長モデル(P = D / (r – g))は、生成AI関連企業の価値形成を説明する鍵となる。ここで、Pは株価、Dは配当、rは割引率(要求収益率)、gは成長率である。このモデルは、rの低下とgの上昇がPを急騰させるメカニズムを示す。
2025年の文脈では、FRBの利下げ継続によりrが低下し、生成AIの成長期待gが上昇している。例えば、NVIDIAの株価はAIチップ需要により急伸しているが、これはモデルが予測する発散リスクを体現する。バブル発生の条件として、(r – g)がゼロに近づく状況が整いつつある。
歴史的バブルの発生メカニズム
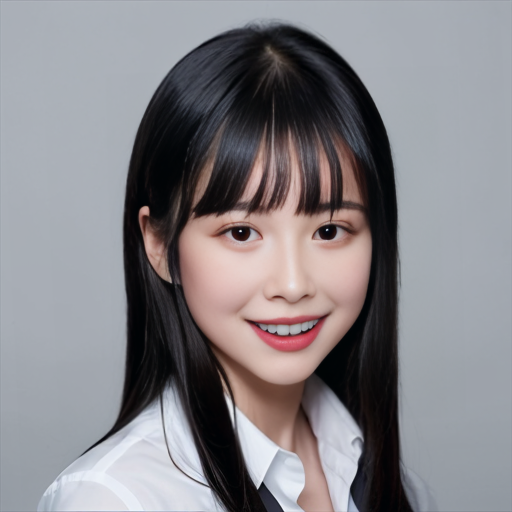
革新的技術・低金利・熱狂は、バブル化の要因になります
過去のバブルは、「需要超過 → 価格高騰 → 過剰投資 → 調整」のサイクルを繰り返す。バブル・トライアングル理論(破壊的革新、豊富な流動性、社会的熱狂)も適用可能である。
- 破壊的革新: 生成AIは、クリエイティブ産業や医療を革新する。
- 流動性: 低金利とベンチャー資金の流入が投機を支える。
- 社会的熱狂: ソーシャルメディアでのAI未来像がフィードバックループを生む。
これらの枠組みは、生成AIブームがバブル条件を満たしつつあることを示唆するが、技術的実態が差別化要因となる。
生成AIブームを巡る議論:バブル支持論と慎重論
生成AIブームのバブル性については、専門家間で意見が分かれる。ここでは、支持論と慎重論を対比し、2025年の最新動向を基に検証する。
バブル化を支持する論拠

金利が低く計算需要が成長する局面なので、AI関連銘柄、特に半導体を供給する企業の株価は、これからバブル化する可能性があります。
マクロ経済的要因
ゴードン成長モデル通り、低金利と成長期待が株価を押し上げる。2025年のFRB政策は、インフレ抑制後の緩和局面に入り、AI投資を加速させる。生成AI企業の時価総額は、2024年からさらに20-30%上昇している事例が多い。
「無限需要」のナラティブ
生成AIの進化(RAGのように多くのトークンを処理する機構や、動画生成や3Dシミュレーション)は、計算需要を無限に拡大する。動画生成AIの台頭により、データセンター需要が爆発し、供給制約が価格を吊り上げる。これは、ドットコム時代のインフラ需要を超える規模である。
歴史的類似
需給逼迫は、リチウムブームや石油ブームに似る。2025年のGPU不足は、過剰投資を誘発し、調整リスクを高める。
バブル論に対する慎重論

生成AIの収益性や計算需要の拡大論に疑問を持つこともできます。そのため、今がバブルのピークだという考え方もあります。
収益性の不透明さ
生成AIの社会的インパクトは限定的との見方がある。既存ビジネスは新しいAIを対して必要としないほどビジネスモデルが洗練されている可能性がある。実際に2025年の調査では、多くの企業がAI投資の回収に苦戦している。
生成AIの収益性が低い場合、AI半導体への投資は経済的合理性を欠き、AI関連銘柄の高い株価は支持されなくなる。
無限需要に対する反論
計算能力は無限に必要になることはない。計算機やそれを動かす電気代の制約と、計算による成果を比較し、経済的合理性(費用対効果を最適化)の範囲で計算が行われるはずだ。
技術革新の本質
生成AIは、メガトレンドとして実態がある。2025年の進展(例: AIエージェントの商用化)は、投機を超えた価値を提供する。バブル崩壊後も、計算インフラが残る可能性が高い。この二面性は、生成AIブームの複雑さを示す。
歴史的バブルとの比較:生成AIの独自性
生成AIブームを過去の事例と比較し、類似点と差異を明らかにする。
二つのバブル類型との類似

GPU/HBMへの巨額投資は英国の鉄道狂時代を連想させます。また、収益モデルが不在のまま事業拡大を行うアプリケーション層企業への投資は、ドットコムバブルを連想させます。
インフラ層と鉄道狂時代
GPU/HBM投資は、1840年代の英国鉄道ブームに似る。
鉄道狂時代は、産業革命後の鉄道という革新的な輸送技術が登場し、多くの資金を集めたが、収益化できない僻地にまで鉄道を敷設し、バブル崩壊に至った。
過剰投資が崩壊しても、インフラが残る。生成AIの場合、たとえバブルが発生し崩壊したとしても、データセンター拡大が長期的社会益を生む。
アプリケーション層とドットコムバブル
OpenAIやStability AIのような企業は、1990年代のドットコム企業に類似。収益モデル不在や赤字拡大のリスクがある。2025年の失敗事例(AIスタートアップの倒産増加)がこれを裏付ける。
独自の「寡占構造」と「階層構造」

今回のAIブームが過去のバブルと決定的に違う点が2点あります。1つは寡占企業により供給がコントロールされやすい点、もう1つは関連企業が階層構造になっており、堅牢さが増している点です。
寡占構造
NVIDIAのGPUシェア(90%以上)とHBMの3社寡占は、過去のバブルを超える。例えばCUDAエコシステムのロックインは、Windows/Intel型支配に近く、需給逼迫を長期化させる。
過去の半導体メモリ(DRAM)ブーム(1980年代・1990年代初頭)では、PC需要の拡大にDRAM供給が追いつかず価格が高騰、一斉投資の結果、供給過剰に転じ、価格崩壊と業界再編を招いた。今回のAIブームは競争が少なく、供給側が価格調整できるという点で、異なっている。
階層構造
生成AI関連銘柄は種別が多い。GPUやHBMなどの半導体を製作する企業(TSMC,NVIDIA,SKハイニックス…)、半導体を保有する企業(Amazon,マイクロソフト,Google,オラクル,CoreWeave…)、半導体を活用する企業(OpenAI,Amazon,マイクロソフト,Google…)に大別される。
この階層構造はバブルの堅牢さを増す。1つの層の売上減は、別の層のコスト減につながり、コストの制約が減ることで需要が息を吹き返す効果を生む。
結論:展望と示唆
生成AIブームは、バブルではないが条件が揃いつつあるハイブリッド現象である。技術革新の実態と投機的要素が共存し、超寡占構造が独自性を与える。
今後の展望
短期的に需給逼迫が続き、インフラ層の優位性が持続。長期的にバブル崩壊しても、安価な計算資源がイノベーションを促進する。
投資家への示唆
株式売却を急がず、長期トレンドを見極める。生成AIの本質を理解し、レイヤー別の価値を評価すべきである。この分析は、2025年の動向を踏まえ、慎重なアプローチを提言する。


コメント