東京大学は日本で一番、学生の学力の格差が大きい。東大入試に合格する最低限のレベルから、上澄みがどこまでも高く飛翔していく光景は、理系の道を志す多くの者にとって、時に残酷な力量の差を突きつける。
杉山聡 氏の著作『微積分+線形代数入門』および『分析モデル入門』は、まさにこの「上澄み」の学力と知能を体現する力作だ。数学、プログラミング、AI、データ分析――あらゆる分野において筆者(私)よりも遥かに深く本質を理解し、しかも若く、その文章からは人柄の良さまでが滲み出ている。この二冊は、理系の世界に存在する力量の残酷な差を、読者にまざまざと見せつけてくれる。
データ分析の「世界地図」を網羅する二大概念書
『微積分+線形代数入門』は、データ分析の根幹をなす微積分と線形代数に特化し、分析への応用を重視して基礎を固める。『分析モデル入門』では、多岐にわたる分析モデルの概念を広く深く扱う。
この二冊が持つ最大の価値は、データ分析と近年のAIの進化に不可欠な重要概念のほとんどを網羅している点にある。これこそ、分析の世界の「世界地図」と呼ぶにふさわしい。単なる数式の羅列ではなく、数式に潜む「考え方」、すなわち各概念がどのように機能し、他の概念とどう繋がっているかという構造的な解説に力が注がれている。
「実装」ではなく「概念」を知ることにこそ価値がある
正直に言って、本書の内容は難易度が高い。「分かった」という確かな実感や手応えを得られない項目も多く、例えるなら、地図を見ただけで現地を訪れたわけではないという感覚に陥る。
例えば、『分析モデル入門』では、初期の画期的な深層学習モデルであるAlexNetの設計思想が扱われている。しかし、この書籍を読んだだけでAlexNetのコードは書けない。重要なのは、実装の詳細ではなく、AlexNetという革新的な「概念」を知り、分析の世界地図にその場所を記すことができたかどうかだ。
というのも、現代においては、概念さえ掴んでいれば、具体的な実装はChatGPTのようなAIが自動でコードを書いてくれる。
本書の極めて高い価値は、「広範な概念の網羅性」に集約される。急速に変化するデータサイエンスとAIの分野において、各技術の位置づけやその背景にある思想を俯瞰する視点を提供してくれる。本書は、データサイエンスを深く理解したい人からAI関連銘柄に投資する株式投資家まで、幅広い読者にとって必携の羅針盤となるだろう。
「知の格差」を突きつけられながらも、読者はこの壮大な地図を手に入れることで、次のフロンティアへの挑戦権を得ることができるはずだ。

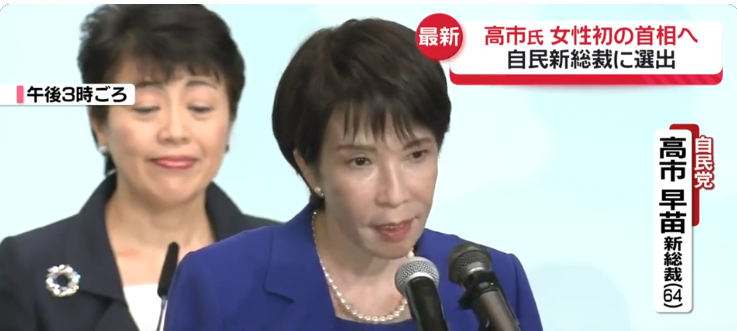

コメント