「会社は株主のもの」という言説の問題点

会社の預金口座にある現金は、会社のものです。株主のものではありません。資産・負債・純資産も会社のものです。
「会社は株主のもの」という主張は、広く受け入れられた自明の理のように語られることが多い。しかし、この言説を厳密に検証すると、原則として不正確であると言わざるを得ない。
株式会社において、会社名義の預金口座にある現金やその他の資産は、法的には会社の所有物であり、株主が直接所有するものではない。同様に、負債も会社が負うものであり、株主が個人的に責任を負うわけではない。資産と負債の差額である純資産もまた、会社の財産として計上される。このように、会社は法人格を持つ独立した主体であり、その財産は会社自身に帰属する。
所有と経営の分離
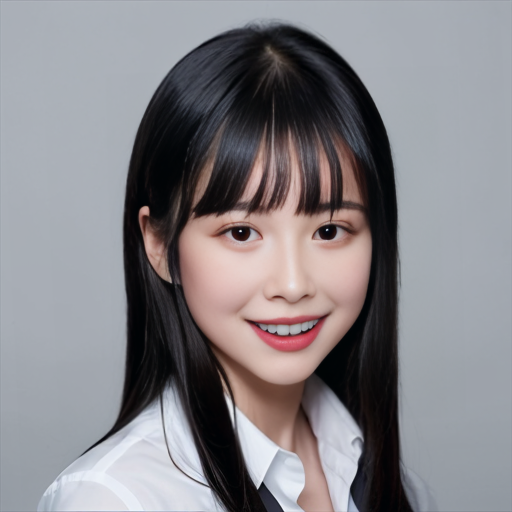
会社の経営は、経営者が行います。株主が行うわけではありません。
さらに、会社の財産を運用・管理する権限は、株主ではなく、株主によって選任された経営者に委ねられている。株主が有するのは、経営者の選任・解任権や配当請求権といった権利であり、これらは間接的なコントロールに過ぎない。したがって、「会社は株主のもの」という主張は、所有と経営の分離という株式会社の基本原則を十分に反映しておらず、解像度の低い見解と言える。

大株主の影響力と「実質的な所有」
もっとも、特定の条件下では、「会社は株主のもの」という認識が現実をある程度捉えている場合もある。株主は議決権を通じて取締役の選任・解任を行い、特に過半数の議決権を握る大株主は、経営陣に自らに都合の良い人材を送り込むことで、会社の財産を事実上支配することが可能となる。このような状況では、形式上は会社の所有物であっても、実質的には大株主の私的財産と見なせる場合がある。

影響の大きな大株主は、会社を自分のものとして扱うことができます。
大株主主導の経営とその影響
しかし、大株主の意向に基づく経営が、必ずしも会社全体の利益や従業員の意向に沿うとは限らない。事業の分割・売却、不採算部門の切り離し、または人員削減といった措置が強行される可能性があり、これらは会社組織や従業員にとって受け入れがたい場合も多い。だが、資本主義経済においては、効率性の追求が最優先とされ、不要と判断された事業や資産、人材が切り離されるのは、ある意味で避けられない流れである。これは、資本主義社会に生きる主体が受け入れざるを得ない宿命とも言えるだろう。

大株主によって会社が食い物にされることがありますが、これは仕方がないことです。
結論:多角的視点からの所有と経営の再考
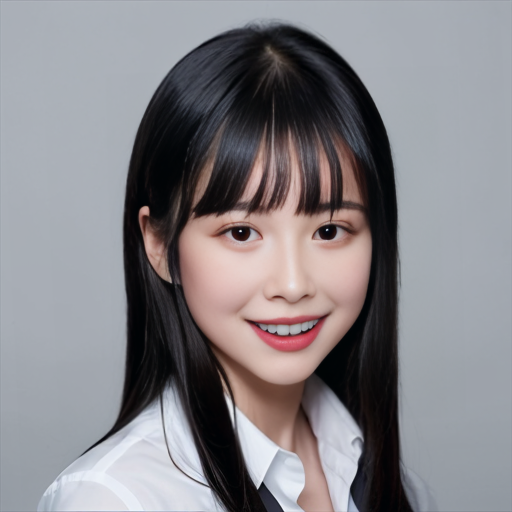
会社のものは、会社のものです。株主のものではありません。ただし、大株主は、会社をあたかも自分のもののように扱える場合があります。
「会社は株主のもの」という単純な図式は、法的な所有権と経営権の所在、そして株主の影響力の範囲を十分に理解しているとは言えない。原則として、会社は法人格を持つ独立した主体であり、その所有者は会社自身である。しかし、現実の経済活動においては、大株主の存在が会社の意思決定に大きな影響を及ぼし、結果として「株主のもの」に近い状態が生じることもある。この複雑な関係性を踏まえ、会社の所有と経営は、より多角的かつ精緻な視点から捉える必要がある。


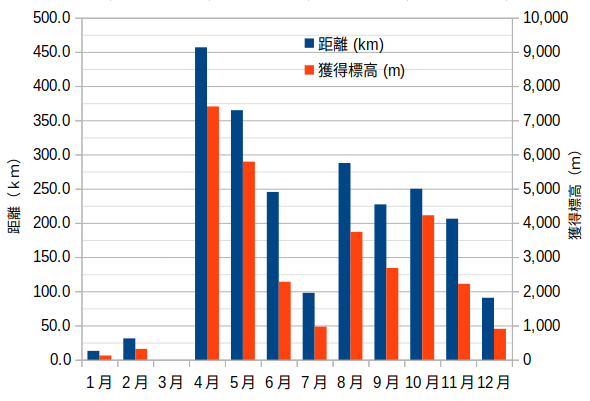
コメント