
デュポン分解とは
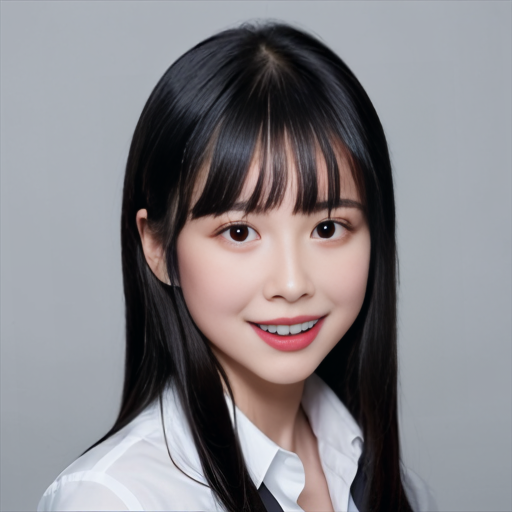
ROE(収益性を示す指標)を、利益率、回転率、レバレッジの3つの要素に分解する分析を、デュポン分解と呼びます。
デュポン分解は、企業の収益性を示す指標であるROE(自己資本利益率)を以下の3つの要素に分解して分析する手法である。
ROE = (純利益 ÷ 売上高) × (売上高 ÷ 総資産) × (総資産 ÷ 自己資本)
この式は、それぞれ以下の指標に対応する:
- 利益率(売上高純利益率)
- 回転率(総資産回転率)
- レバレッジ(財務レバレッジ)
この分解は単なる数学的操作に過ぎないが、デュポン分解を用いることで、企業の収益性の構造を深く理解できる重要な知見が得られる。
ROEの収斂傾向と市場原理

「ROEはどの企業もだいたい同じ」に注目すると、デュポン分解の各要素の意味や、ビジネスモデルの理解が深まります。
デュポン分解の分析を深める上で注目すべきは、長期的に多くの企業のROEが一定水準に収斂する傾向がある点である。ROEが高い(収益性の高い)ビジネスには新規参入が増え、競争の激化により収益性が低下し、ROEが下がる。一方、ROEが低いビジネスからは企業が撤退し、競争が緩和されることでROEが上昇する。この市場原理により、ROEは平均的な水準に落ち着くと考えられる。
この収斂傾向を踏まえ、デュポン分解を活用することで、企業がどの要素で収益性を確保しているか、あるいはどの要素に制約があるのかを明確にできる。これにより、企業のビジネス特性や競争環境を深く理解することが可能となる。
各種ビジネスモデル
デュポン分解のどの要素に強みがあり、どの要素に制約があるかで、ビジネスモデルを分類できる。
利益率重視のビジネスモデル
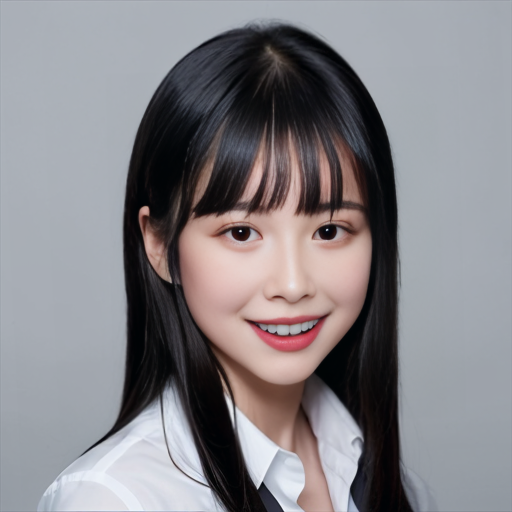
ソフトウェア企業や、大規模な設備投資を行う企業は、利益率を高くして稼ぎます。
利益率を高く維持できる企業には、以下のような例がある:
- ソフトウェア企業(例:マイクロソフト):原価が低く、高い利益率を確保しやすい。
- 設備投資型企業(例:TSMC):巨額の投資が新規参入の障壁となり、高い利益率を維持。
ただし、これらの企業は大規模な設備投資が必要な場合が多く、総資産回転率が低くなる傾向がある。また、保有資産の担保価値が限定的で、景気変動時の貸し剥がしリスクも考慮されるため、財務レバレッジを高く設定しにくい側面がある。
回転率重視のビジネスモデル
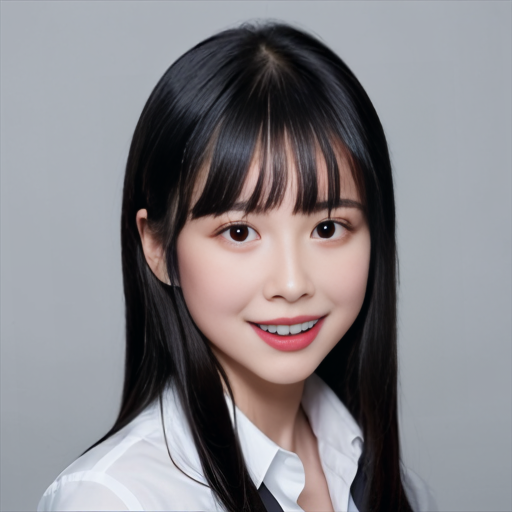
小売業は、回転率を高くして稼ぎます。
総資産回転率を高くできるのは、小売業などの業種である。これらの企業は商品の回転を早めることで売上を最大化するが、薄利多売のビジネスモデルを採用するため、利益率は低くなる傾向がある。さらに、在庫など担保価値が限定的な資産構成であるため、財務レバレッジを高く設定することは難しい。
レバレッジ重視のビジネスモデル

銀行や不動産会社は、レバレッジで稼がなければなりません。
高い財務レバレッジを活用できるのは、銀行業や不動産業である。これらの業種は、金融資産や不動産を担保に資金調達が容易であり、総資産を自己資本の何倍にも膨らませて事業を展開できる。しかし、以下のような制約がある:
- 銀行業:債券投資の利ざやが薄いため、利益率が低い。
- 不動産業:開発から販売・引き渡しまで長期間を要するため、総資産回転率が低い。
これに対し、食品小売業など商品回転率の高い業種と比較すると、回転率の差は顕著である。
デュポン分解の意義
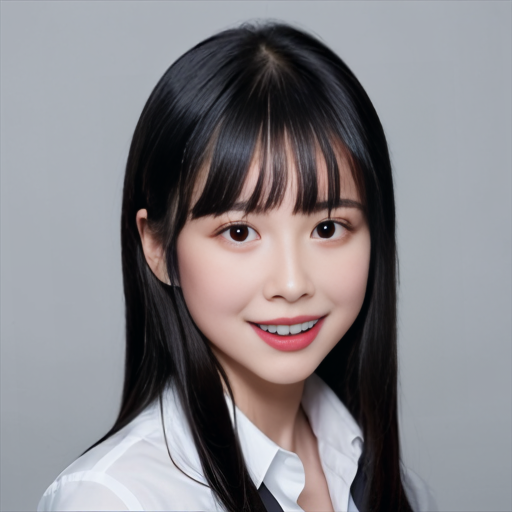
デュポン分解で、企業の強みや制約が良く分かりますね!
デュポン分解は、単なる財務指標の分解を超え、ROEの収斂という市場原理を背景に、企業や産業の構造的な強みや制約を浮き彫りにする強力な分析ツールである。各企業のビジネスモデルの特性を理解し、収益性の源泉や競争上の課題を特定する上で、極めて有効な手法と言える。


コメント